上の娘が産まれて右も左もわからない時に頼ったのが「育児本」です。
何冊も読みあさって「ちゃんとした子育て」をしようと奮闘しました。
あれから4年半がたち、振り返ってみると思い通りにいかない事もたくさん。
ぜんぜん「ちゃんと」なんて出来てこなかったなぁ、とつくづく実感しています。
それでも子供たちは「ちゃんと」成長してくれて、毎日毎日頑張っていてくれて…
時にはビックリするくらいたくましく、一歩ずつ成長してくれています。
今回は父親になりたての僕が、どんなことを学んで実践しようとしていたのか?
最初に読んだ3冊の本をとりあげて、初心に戻ってみようとおもいます!
女の子の育て方 「愛され力」「自立力」「幸福力」を育てる83のこと
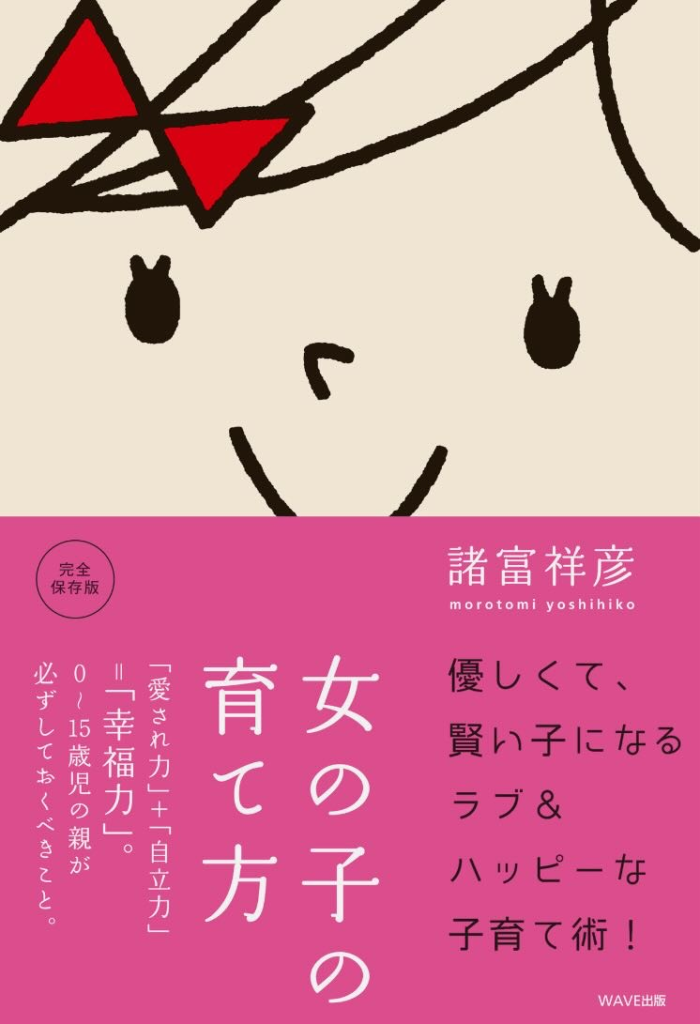
女の子の育て方 「愛され力」「自立力」「幸福力」を育てる83のこと
諸富祥彦氏著
まずは「女の子の育て方」。いまだに「未知」の生物「女の子」に対応するべく購入しました。
この本では、母親が自分自身を大切にし、幸せで輝いている姿を見せることが、娘にとって非常に大切だと強調されています。母親が自分の人生を楽しみ、自己肯定感を持っていると、娘もその姿を見て自然と自信を持つようになり、自分の人生を前向きに切り開く力を育むことができるというメッセージです。
年齢に応じた関わりを意識しよう

親が年齢に応じた適切なしつけと愛情を注ぐことが、子どもの成長と幸福に直結します。
0~6歳は「ラブラブ期」できるだけ愛情を注ぎ自己肯定感を育む
自己肯定感が最大のプレゼント
「抱っこ」や「タッチング」でスキンシップを!
言葉に出して、具体的に愛を伝える
6~12歳は「しつけ期」家庭のルールを教え、ポジティブに接する
社会のルールに自分を合わせる術を学ぶ時期
ポジティブな言葉を使う(なんて悪い子なの!といった言葉はNG)
自発的な行動や判断を尊重する
「我が家のルール」はシンプルに
12~18歳は「見守り期」子どもの自立を支援する
自分で乗り越える力を身につける時期
10歳になったらお母さんは家庭に入るのがベスト(10歳~15歳は学校などで不安定になりやすい)
口出しし過ぎず見守る
学力を伸ばすために心がけること
勉強は親子で一緒に楽しみ、子どもが自分から学びたいと思える環境を作ることが大切です。
家庭での学習
勉強を始めるとき、最初の10分は一緒にやることで「スイッチON」
早期学習は子どもと親が楽しめるものを
学校の宿題だけでもOK。毎日勉強する習慣を
学校選び
公立か私立かではなく ”子どもに合った校風” を選ぶ
荒れていないかリサーチ
恋愛・結婚力の育て方
自分の事を大切にできる人ほど恋愛や結婚で上手く傾向にあります。
自己肯定感を育てると「愛されオーラ」がでる
夫婦ケンカはきちんと解決して仲直りすればOK
ちゃんと自分の意見を言える家庭にする
性教育
正しい知識を親が伝える(愛情があるならコンドームをつける等)
恥ずかしがらずに興味を持ち始めたら話をしよう
思春期の人間関係について

友人関係の管理。SNSの使用にルールを設け、友人関係の悩みには「寄り添う」を心掛ける。
友人関係
女の子は友達が仲間のグループから仲間はずれにされ板挟みになる等、様々なトラブルが起きやすい
そんな時は、アドバイスするより気持ちに「寄り添う」ことを心掛ける
SNSの注意点
いじめの温床になったり、仲間同士の同調圧力から「すぐ返信しないと」というプレッシャーを感じてしまう
ルールを話し合う(個人情報は漏らさない、プロフは利用しない等)
悩んでいる子どもにかけてはいけない言葉
「あなたにも悪いところがあるんじゃないの?」→否定のメッセージ
「あなたさえ気にしなければ」→軽く聞き流された感覚
「もっと強くなれ!」→親の欲求
つらいことがあった時、悩みを打ち明けてくれる関係をつくっておくことが大切。
徹底的に味方でいてあげよう。子どもの「安全基地」になろう。
母と子の絆を深める
母親自身の心身の健康を大切にし、家庭内で夫婦の役割分担をしっかりと決めておきましょう。
女の子は想像以上に「お母さんの期待に応えたい」とおもっている
子どもに「期待」するのではなく=「応援」する
母親は娘を自分の一部として捉えがちです。一人の別の人格ということを忘れない
グチを言わない(娘をカウンセラーにしない)
「笑顔ばかりの家族」ではなく「何でも言える家族」をつくる
幸せな人生を送れる女性に育てるために
ゴール=娘の幸せな人生
幸せに向かって必死に努力する力をやしなうために、先回りして与えすぎない
本当に欲しがっているものだけ、誕生日など特別な日に買い与える
望ましい「𠮟り方」
低めの落ち着いた声で、ゆっくりと話しかける
じっと子どもの目を見て、語りかける
何がどうダメなのか「具体的に」叱る
悪いことをしたときに「すぐ」叱る
「没頭できる何か」を見つけるために
何かに夢中になれるものを見つけたら伸ばしていけるように見守る
「働く楽しさ」を知っている女性に育てよう
「専業主婦を目指す」選択はリスクが高い(離婚、リストラ、死別 etc)
働く楽しさ、世の中の役に立っているという感覚を持てるように
お父さんやお母さんの仕事仲間から直接話を聞く機会を設けると良い

この本から学んだ事
自分を大切にできる人になれるように年齢によって適切な接し方があるということ。特に思春期の年代は難しい対応に迫られるケースも想定されます。
そんな時に悩みを「相談」してくれるような親子関係を築かないといけないということを学びました。「女の子」の心のケアには母親の存在が大きく、父親としてはその母親をフォローできるよう夫婦で協力し役割分担をしなければいけません。
また、母親が幸せでいることが「女の子」の幸せな人生をよぶ原動力になります。父親にできる事は、出来るだけ母親の負担を減らし、いつでも笑顔の母親でいてもらえるようケアする事ではないでしょうか?
子どもの才能を伸ばすパパとママの習慣
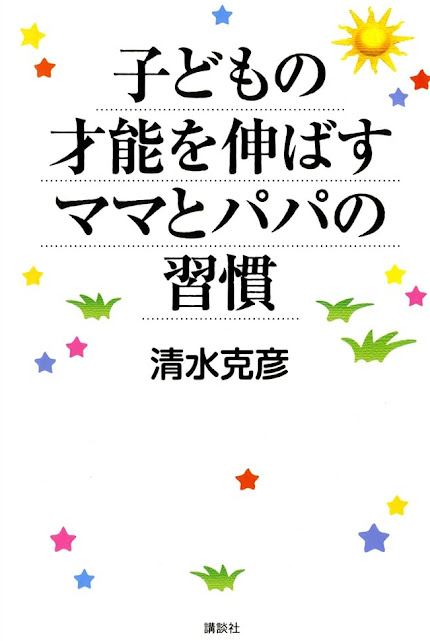
清水克彦著
この本の主張は、「親の関わり方次第で、子供のやる気や成長が大きく変わる」ということです。大切なのは子どもが「主体的に学び」、「挑戦し」、「成長できる」ということ。そのために親は環境を整えて適切なサポートをすることが重要です。
具体的な4つのポイントを見ていきましょう
やる気を引き出す話し方

声の掛け方によって子供は好奇心をもって物事に取り組めるようになります。
ほめるスキル
何かか少しでも上達した時や、自分からすすんで何かをやり遂げた時
例えば「毎日ドリルをがんばった からだね、パパえらいと思うよ」などと頑張りをほめる
成段が下がった子供にも頑張りをほめましょう
「前より〜は出来てるから、問題は~だね」と前向きな声掛けが好ましいです
「どうして出来ないんだ~」「~ちゃんは出来るのに」のように問い詰めたり、ほかの子と比べてはダメ
子どもに小さな成巧体験を頼み上げさせて それを大げさにほめてあげる
本気でやれば出来んだと感じることで物事に取り組む姿勢がポジティブになる
努力をほめる
否定的な言葉 「ダメじゃないか!」「努力が足りないぞ!」というメッセージを受けとると失敗から学ぼうとせず、向き合うことをやめてしまいます
上手く行った部分をほめて、上手くいかなかった部分は「アドバイスをする」など次につながるメッセージをおくることが大切です
頑張って上手くいかなかったら結果はともかく頑張りをほめる
頑張って結果が出ないのは 頑張らなかった時よりショックが大きい
親が一緒にやってみる
親子でいろいろな体験をすることで、子どもの関心やモチベーションを高めることができます
親が何かにチャレンジしている姿をみせるのも子どものチャレンジ精神を高めます
発想力を育むには
例えば「木の幹を紫色に塗る!」といった ”奇抜な発想” に対して「周りがどう思うか?」といった理由でやめさせたりしない
着眼点やアイデアを評価し失敗を恐れず挑戦する子を育てる
自発的に取り組める子にするために
親が一番のコーチになる
傾聴:話しを聞く姿勢を見せる
質問:なるべく疑問形で語りかけをする(押しつけをしない)
親がブレないことが重要です。ポリシーを覆すと親子の信報関係が損なわれる結果になります。気分でいうことを変えない一貫した姿勢が大切です。
また、親が自分たちを低く見せるような態度も良くありません。たとえそれが謙遜だったとしても子どもは親を手本に出来なくなってしまいます。
ママッて素敵、パパってカコイイと思える事が大切
子供に興味を持たせる環境づくり

「やってみたい!」という気持ちを引き出す環境づくりが親の役割です。
好奇心を育てる
家族がそれぞれ夢をかたりあうような家庭環境が子どもの好奇心を伸ばし夢を育みます
親が地域の行事に参加するなど社会との繋がりを持つ事で子どもは社会への関心を持ちやすくなり
ママやパパが様々な活動を楽しそうにおこなうと「自分もやってみたい」という気持ちににつながります(星空観測など)
興味をもたせるキーワード
男の子「かっこいい」 女の子「かわいい」
「才能ある」「センスある」は物事に興味を持ちやすい
本当に好きな事を見つける
何でもやらしてみて様々な経験や多くの場数がしっかりした子を育てる
スポーツ、絵画など本物を見せる(プロの試合や美術館、音楽イベントなど)
子どもの質問にはすぐ答える
子どもから質問があった時は、何につまづいているか?一緒に調べ最後は子供がまとめるよう促す
自分の手に負えないような事柄は(学校の先生などに)「どう聞けばいいか?」をアドバイスする
子どもの「なりたい」をかなえる方法
子どもが自分で「前に進むための力」を養っていくための考え方です
子どもの夢を叶える力
子どもの抱いている夢は否定せず、強力な応援団になる
子供のファンタジーを壊さず、夢を追いかける仲間をつくれる環境を用意する
目標や計画を明確にする手助けをする(マニュフェストを作る)
夢を叶えるためのロードマップを作成して、予算なども考慮しておく
子供の性格によって戦略をたてる
SWOT分析
目標達成のために 強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats) を整理し、最適な戦略を立てる方法です。もともとはビジネスで使われるフレームワークですが、子育てにも応用できます。
子どもの成長や夢の実現に向けたSWOT分析の活用方法
S(強み Strengths)→ 子どもの得意なことや長所
例:好奇心が強い、集中力がある、運動が得意、計算が速い
W(弱み Weaknesses)→ 子どもが苦手なことや改善すべき点
例:飽きっぽい、苦手な教科がある、人前で話すのが苦手
O(機会 Opportunities)→ 子どもの成長を助ける環境やチャンス
例:好きな分野の習い事やイベントがある、良い指導者に出会える、親が協力できる
T(脅威 Threats)→ 目標達成を妨げる可能性のある要因
例:時間が足りない、ライバルが多い、やる気が続かない
SWOTを活用して、子どもの「得意を伸ばし、苦手を克服する」計画を立てる
強みを活かせる環境を整え、機会を増やす
目標達成の障害を事前に把握し、対策を考える
夢や目標の共有
家族が夢や目標を見やすく共有して、それぞれの夢を応援しあう
予定表などに進捗状況を書き込む
歴史などから理想の人物の成功事例たストーリを語りあう
ときには一喝も
「僕にはムリ」「私にはできない」などの諦めそうな時や約束を破った時には必要な場合も
叱る時には以下のことに注意しましょう
- 感情はコントロールする
- 人格否定しない
- 他と比較しない
- 突き放さない
感情的にならないよう心掛けて伝えるようにしましょう
個性をスポイルしない
一般的な考えを強制して他に合わせようとはしない
型からはみ出すのは才能の証である
人前で子どもの事を悪く言わない
褒められた時謙遜して「うちの子なんか」と言わない、褒められた時は「ありがとう」で良い
長所を伝えて、素直な子に育てましょう
子どもの興味を助ける
ノートに目を通して「字がきれい」「工夫されてる」「整理されてる」と具体的にほめてあげる
「いつまで図鑑ばかり見てるの?」や「勉強しないとサッカーやめさせるよ」といったよう、に子供が熱中している事に水を差さない
これもできるならあれもできるよと子供の視野を広げる提案をしてみる
責任感を持たせる
家事の手伝いや自分の机、カバンの整理などををさせる
忘れ物を届けない([困る]という経験も必要)
「待つ」「任せる」「見守る」の3つのMを意識して関わろう
子供の人間力を高める習慣

たくましく生きていく準備をするために心がける事です。
勝負事の経験(スポーツ、発表会など)を通じて努力の大切さを学ばせる
自分のことは自分でやらせる(例:レストランでの注文をじぶんでさせる)
親自身が自信を持ち、笑いのある家庭を作る
お金の管理を学ばせる(自分のお小遣いのやりくりするスキルを身につける)
守れない約束はしない。守れる約束は確実に履行する
この本から学んだ事
子どもの才能を伸ばして将来「やりたい事」を実現できるよう「自分でやる力」を育てていくことが大切。親の「こうするべき」を押し付けないようにしながら、子どもが自分で没頭できることをみつけて伸ばしていいけるよう、環境を整えサポートすることが親の役割なんだと学びました。
私たちは子どもに何ができるのか 非認知能力を育み、格差に挑む
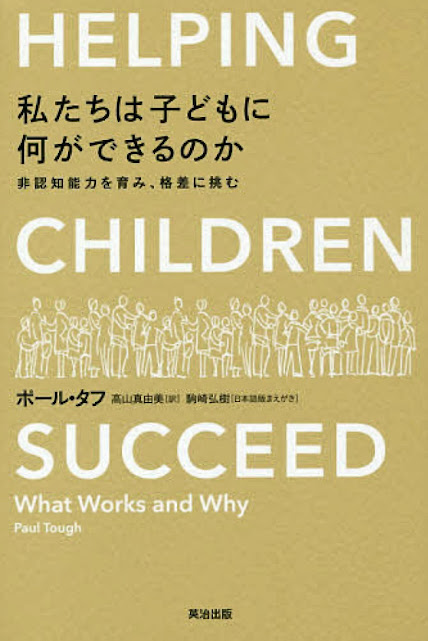
私たちは子どもに何ができるのか 非認知能力を育み、格差に挑む
ポール•タフ著
メンタリストDaiGoさんのお勧めでよんでみました。
「子どもの将来の成功や健康は、幼少期の環境や親の対応によって大きく左右される」
特に、非認知スキル(やり抜く力・自制心・好奇心など)が重要であり、それを育むには、安定した家庭環境や、ストレスに適切に対応できる親の存在が必要です。しかし、貧困や不安定な家庭環境があると、子どもの発達に悪影響を与え、健康や行動面でのリスクが高まります。
そのため、個人の努力だけでなく、社会全体で環境を改善することが不可欠であり、教育や社会政策の見直しが求められる、という主張をしています。
子どもの成功に必要なスキル
子どもの将来の成功(キャリア、幸せ)を実現するためには、”読み書き” ”計算” ”分析能力” などの「認知スキル」だけでなく
”やり抜く力” ”好奇心” ”自制心” ”楽観性” ”誠実さ” といった「非認知スキル」が大きく影響します
「非認知スキル」をたかめるために最初に働きかけるべきは環境
幼少期のストレスが最も大きな悪影響を与えます
親の対応によって、子どものストレス対処能力が決まる

親がどのように関わり環境を整えていくべきか
親の厳しい対応 → 強い感情の処理が苦手に
親の落ち着いた対応 → ストレス耐性が向上
乳幼児期の環境が特に重要
乳児期、子どもは泣くたびに、感情の処理方法を学んでいます
丁寧な対応をすれば、不快な感情への対処が上手にできるようになるのです。
人生最初の3年間に脳の発達が決まり、
特に最初の12カ月間、温かく気配りの行き届いた子育てを受けると、安心感と自信が根付きます。
逆境やトラウマの影響
幼少期のストレスは身体・精神両面に悪影響
逆境の中で育てられた子供は以下のリスクを背負うことに…
ガン・心臓病・肝臓病が2倍、慢性気管支炎が4倍
アルコール依存症が7倍、学校での問題行動が17倍
乳幼児期の親の口論が、感情・ストレス反応・自制に関わる脳に悪影響
内発的モチベーションを育てる
主体性をもって取り組める人間になるために「内発的モチベーション」を持つことが大切です
「自立性」
自分で選び、意思を持って取り組むこと、自分でコントロールして進めていくことが大切です
「有能性」
簡単すぎず、挑戦できる課題に取り組む。自己効力感を養い「何でもできる!」という自信になります
「関係性」
価値を認められ、尊重される環境。人の役に立っているという感覚がモチベーションをたかめます
マインドセットの重要性
① 私はこの学校に所属している
② 私の能力は努力で伸ばせる
③ 私は成功できる
④ この勉強には価値がある
このようなマインドセットを持つことで、自信を持って物事に取り組める下地が出来上がります

環境を改善するために必要なこと
社会問題としての子どもたちに必要な環境整備について以下の3点があげられます
家庭環境
親の安定した良好な関わりが重要です。貧困や虐待により適切なかかわり方をされていない子供たちに社会としてどう対応していくのかという問題です
学校環境
帰属意識と目的意識を持てる教育の場が理想です。荒れた学校やいじめ問題など個々の対応では解決できない部分をどう改善していくべきなのかが課題です
教育の質
意欲を引き出す教師の存在が理想です。学校や個人単位での質のばらつきなど、どのような方向性で改善すると良いのでしょうか?
社会政策の見直しが必要!
今こそ、どうすれば子どもにとって良い環境を作れるか真剣に議論すべき!
この本から学んだ事
「非認知能力」を育てるには「子どもが安心できる環境」が大切だという事。幼少期は親が愛情をもって子どもの「不安」などをケアし、学校が始まったらできるだけ良い環境を選んで進学させてあげる必要があります。できるだけ子どもが自分ではどうしようもないことにストレスを感じないように導いてあげることが親の役割だと学びました。
まとめ
どの本にも共通したメッセージがありました。
1,安心できる家庭環境 2,自主性を育て自分で考え行動する力を養う 3,いざという時に助けてあげられること
親の役割は手を引っ張っていってそこに立たせるのではなく。子どもがどこに行きたいのか自分で選んで進めるように見守り、時々手をかしてあげる事なのでしょう。
まだ、上の娘がうまれて4年半、下の娘がうまれて1年半。本当に大変なのはこれからなのかもしれませんが。あらかじめ想定して準備できるように読み返してみて良かったと思います。
毎日、最高に素敵な日々を与えてくれる子どもたち。幸せになってもらうためにできるだけ頑張ってみます!
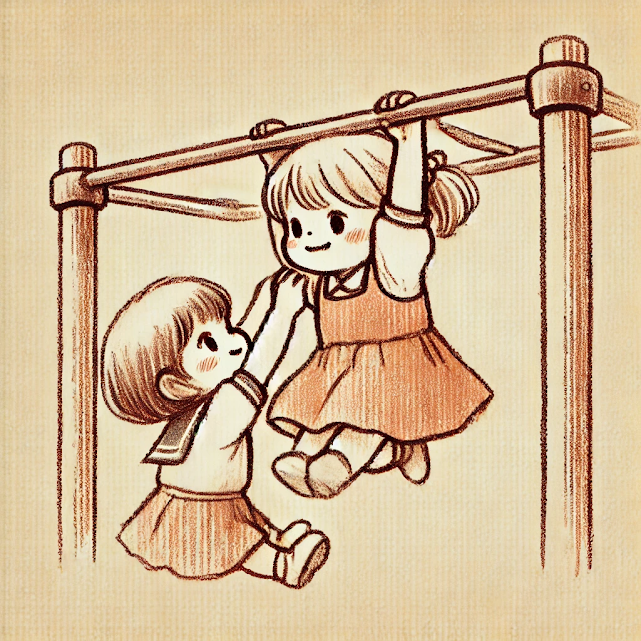



コメント